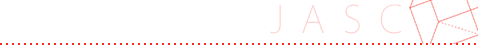会長の挨拶
第18期会長挨拶

日本犯罪社会学会
第18期会長 浜井浩一
本学会も設立から50年を迎え、2023年10月に立正大学において50回目の大会を開催しました。そこで第17期に続き、第18期の会長として選出されました。どうぞよろしくお願いします。
第50回大会を記念して企画されたテーマセッション「日本犯罪社会学会の創成期を語る」において、本学会が発展してきた背景には、学際性だけでなく、学術団体特有の権威性が排除され自由闊達な議論が行われていたことにあるとの指摘がありました。また、第50回大会では、立ち直り研究の第一人者であるShadd Maruna先生による記念講演を企画し、元受刑者などの当事者が犯罪学の理論と想像力に与える影響についてご講演いただきました。そこで、Maruna先生は、立ち直りのプロセスを知っているのは当事者だけであり、立ち直った当事者が自らの物語を語ることで、刑事司法の在り方そのものを変えていく可能性について言及されました。その後の大会シンポジウムでは「包摂概念を見直す」と題して、当事者性や多様性、レジリエンスが称揚される現在、包摂概念を見直し、境界線の引き直しについて、当事者が既存の社会そのものを変えていく可能性を含めて議論が行われました。第17期の会長挨拶の中で、会長としての抱負として、「本学会の持つ学際性と多様性の伝統をさらに発展させることで、犯罪学の持つ可能性を追求していくことだと考えています。」と書きましたが、最近の大会では、大学等の研究者や実務家に様々な当事者が加わることで議論に深みや広がりが生まれていると思います。もちろん、本学会は学術団体であり、会則第2条に「本会は、犯罪社会学の発展・普及および研究者相互の連携・協力をはかることを目的とする。」とあるように、実務家や当事者、さらには犯罪社会学に関心を持つ人たちが、犯罪社会学を研究する研究者として議論に加わることが重要であることは言うまでもありません。
第17期の全国理事会や総会での会長就任あいさつでは、「世代交代」と「感謝と恩返し」という二つのキーワードを挙げさせてもらいました。第18期は、この思いを引き継ぎつつ、大学等研究環境の変化などに対応し、学会や大会運営の持続可能性を図るために、財政面を含めて様々な改革に着手していかなくてはなりません。次世代にバトンタッチするためにも、常任理事会を構成する各委員会の委員長などの世代交代を進めつつ、一つ一つの課題に取り組んでいきたいと思っています。研究者としての私を育ててくれたのは日本犯罪社会学会です。その恩に報いるためにも、もう3年間、研究と実務、そして世代間の架け橋となることで本学会が更に発展できるように微力を尽くしてまいりたいと思います。
以上